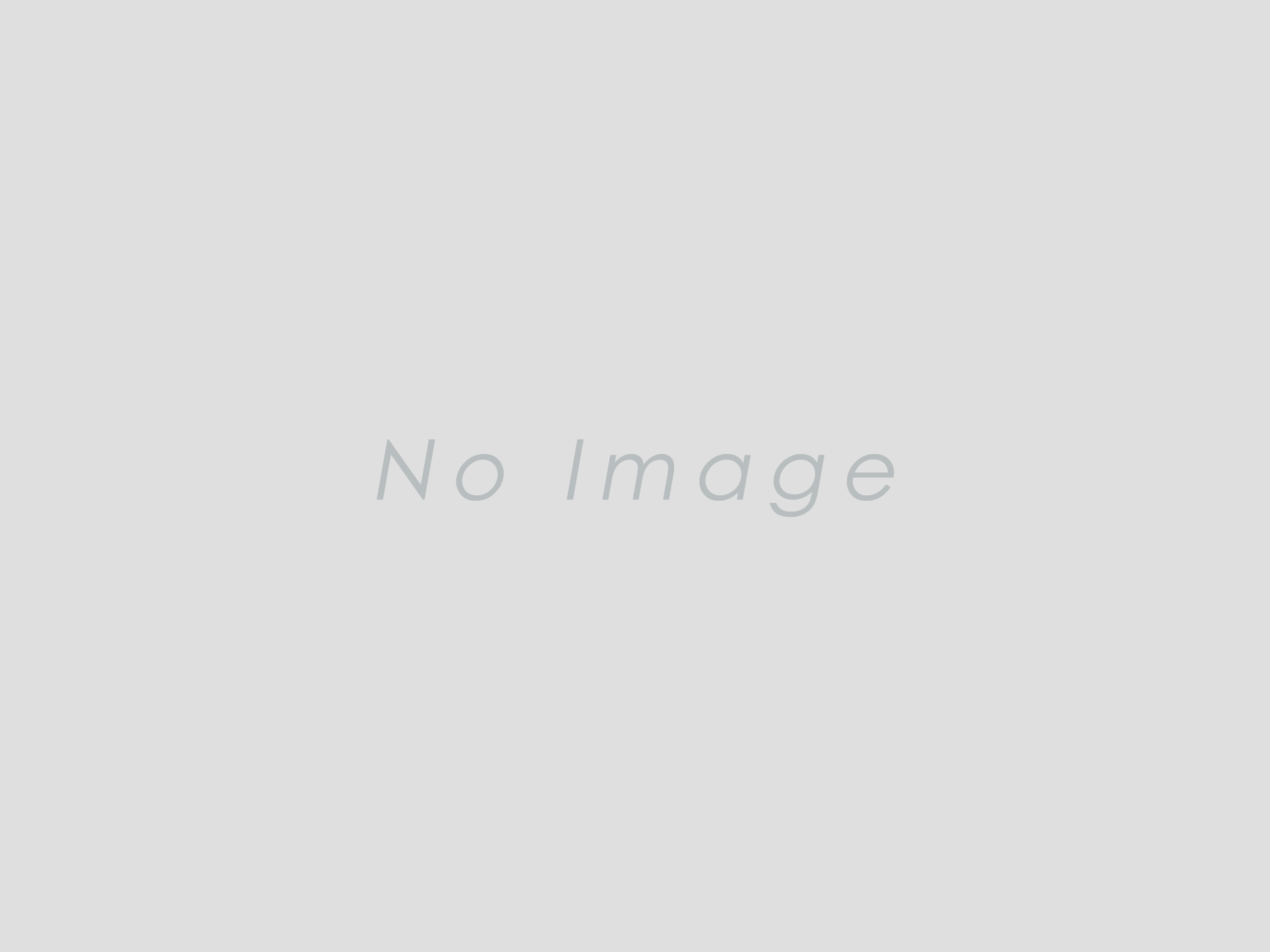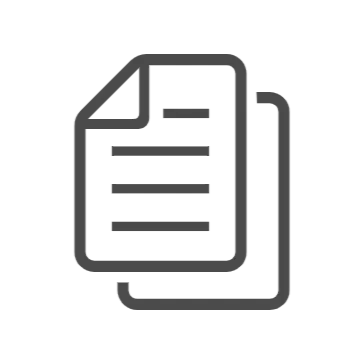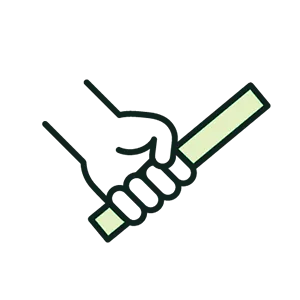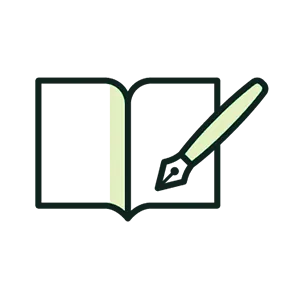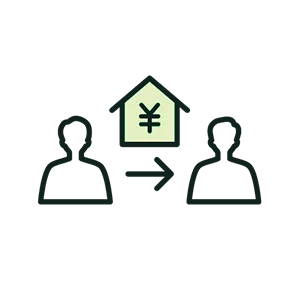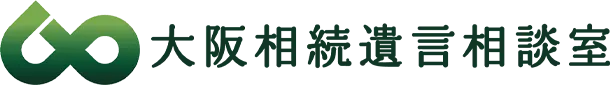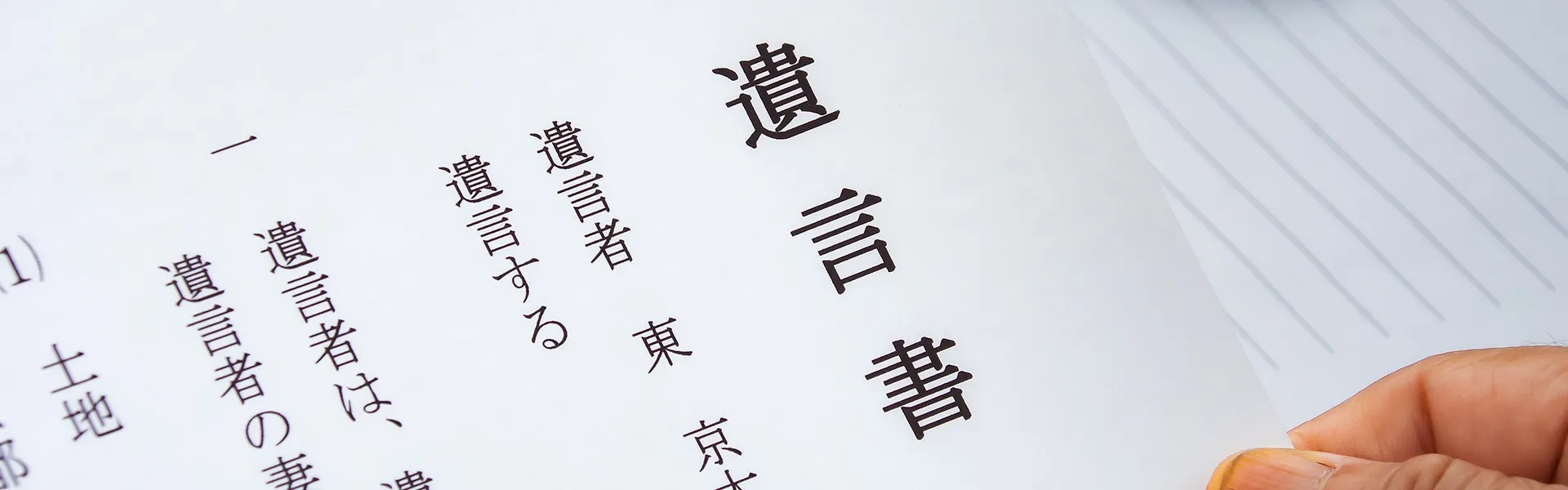柔軟な対応でお悩み解決をサポート
サービス
当事務所へご依頼いただける主なご相談内容をまとめています。
紹介している分野以外にも幅広く承っておりますので、少しでもお困りの際はお気軽にご相談ください。
一人ひとりと信頼関係を築きながら相談
ご紹介
法律の専門家がチームとして連携し、家族信託や成年後見といった法的支援を求める方々に寄り添いながら、遺言書の作成から不動産相続の取り次ぎ、相続手続までを一貫してサポートしております。生前対策における最大の目的は、大切なご家族やご親戚間の争いを防ぎ、相続が突然発生した場合でも故人様の意志のままに資産を円滑に承継することです。大阪で顧客満足度No.1をモットーに掲げ、相談者様の数だけ異なるさまざまなニーズに真摯に向き合い、一人ひとりと信頼関係を築きながら生涯にわたってサポートし続けてまいります。
よくいただくご質問とその回答を掲載
よくある質問
不動産や家族信託に関することなど、特に多いご相談内容を厳選してスタッフの回答とともにまとめています。事前にご覧いただくことで、疑問や不安の解消に導きます。
- 遺産分割はどのように進めるのでしょうか
- 遺産分割協議を成立させるためには、全ての相続人の合意が不可欠です。問題がこじれてしまうと、解決が難しくなりますので、できるだけ早い段階で専門家に相談することをお勧めします。
- 不動産の相続登記や銀行預金の名義変更の手続きのみを依頼できますか
- もちろん可能です。ご相談の際には各手続き費用のお見積もりをさせて頂きますので、ご自身でなされる手続きと当方にご依頼いただく手続きを選択していただくことができます。
- 相続人の中に付き合いのない人がいるのですが大丈夫でしょうか
- 相続人をお調べする過程でご住所等が分かりますので、連絡して頂くことも可能です。ご希望があれば当方からお手紙をお送りします。
- 相続税の申告もご依頼できますか
- 当事務所で直接お受けすることはできませんが、信頼できる税理士を紹介させていただきます。税理士と情報を共有させていただくことでスムーズに手続きをすすめることができます。
- 遺言にはどのような種類がありますか
- 主なものとして遺言者が遺言内容、年月日、氏名を自書する自筆証書遺言と
遺言者の述べた内容をもとに公証人が作成する公正証書遺言があります。
- 自筆証書遺言の長所、短所について教えてください。
- 長所としては、遺言の作成、内容を誰にも知られないこと、費用がかからないことが挙げられます。
半面短所としては内容が不明瞭であったり、民法で決められた方式に違反する場合に無効になる恐れがあるとことや他にも他人に隠匿されたり、改変、破棄される恐れがあったり、そもそも発見されない恐れがあります。
又家庭裁判所の検認手続きが必要になることが負担になることもあります。
- 公正証書遺言の長所、短所について教えてください。
- 長所としては法律の専門家である公証人が作成するので、方式違反や内容が不明瞭で無効になることはないこと、原本が公証役場に保管されるので、他人に改変、破棄、隠匿される恐れがないこと、家庭裁判所の検認手続きが不要であることが挙げられます。
半面短所としては証人が2名必要であることや作成にあたって費用が必要であることが挙げられます。
- 遺言を書くべきなのはどのような場合ですか
- 例として挙げるなら
① 夫婦に子供がいない場合
② 前妻(夫)の子供と後妻(夫)がいる場合
③ 内縁の妻(夫)に財産を譲りたい場合
④ 息子の嫁に財産を譲りたい場合
⑤ 孫に財産を譲りたい場合
⑥ 海外に相続人がいる場合や音信不通の相続人がいる場合
⑦ 身寄り(相続人)がいない場合 などです。
- 認知症になると不動産の売却が難しくなると聞きましたが、何か良い対策はないでしょうか?専門家に依頼する費用や裁判所への手続きが煩わしいため、成年後見制度は避けたいと考えています。
- 信頼できる家族を受託者に指定し、不動産の管理や処分を任せる「家族信託」という方法があります。これにより、認知症が発症した後でも、ご家族が代わりに不動産の売却や管理を行えるようになります。
- 家族信託は、認知症の方でも利用できるのでしょうか?
- 家族信託は、信託契約を結ぶことで効力を持つため、当事者には契約を結ぶための判断能力が求められます。したがって、すでに認知症を患っている方は契約を行うことができません。高齢者の場合、突然症状が変化することもよくあるため、「ちょっと不安だな」や「物忘れがひどくなってきた」と感じたら、早めに対策を講じることが大切です。
- 先祖代々の土地を、私が亡くなった後も私の血縁者に引き継いでもらいたいと考えています。長男には子供がいない一方、次男には子供がいます。まずは長男に土地を引き継がせたいのですが、長男が亡くなった際にその妻や親族に財産が渡る可能性があると聞きました。何か良い方法はありませんか?
- 受託者を次男の子(孫)にし、第一受益者を長男、第二受益者を次男、第三受益者を次男の子(孫)と設定した家族信託契約を結んでおくことで、長男の妻の親族に財産が流れるのを防げます。これにより、先祖代々の土地は長男から次男、さらに次男から孫へと引き継ぐことが可能になります。
- 障害を持つ子どもの将来について心配しています。子どもが自分で財産を管理できないため、私たち夫婦が亡くなった後に兄弟に世話をお願いすることはできるのでしょうか?
- 可能です。兄弟を受託者にして、ご夫婦の財産を信託する方法があります。ご夫婦が亡くなった後、兄弟はその財産から障害を持つ子どもの生活費や施設利用費を支出し、親に代わって子どもの生活を支えることができます。
複雑な法の知識を一つひとつ解説
コラム
法律に関する疑問や不安を解消するヒントとして、有益な情報を幅広く発信しています。
生前対策や遺産となる不動産の管理方法、遺言作成のポイントなども解説いたします。
事務所のお知らせや活動報告など紹介
ブログ
スタッフから日々の活動や業務に関連する新着情報などをお届けしています。アットホームな事務所の様子もお伝えし、ご相談いただきやすい環境を常に整えております。